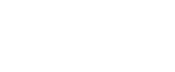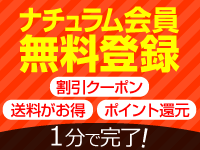2016年07月12日
で進む馬のうしろで
それから数日後の朝、台所をこそこそとかぎまわりつづける老人にたまりかねて、ポルおばさんがいやな顔をしはじめたとき、老人はある用件で近くのアッパー?グラルトの村へ行ってくると言い訳した。
「願ってもないわ」ポルおばさんはいささか無遠慮に言った。「あんたがいないあいだは少なくとも食料品室は安全でしょうからね」

老人はおもしろそうに目をきらめかせてふざけ半分にお辞儀をした。「何か入要なものはないかね、マダム?ポル? ちょっとしたものなら買って来てあげられるよ――どのみちわしの手に届く程度のものだよ」
ポルおばさんはすこし考えた。「香辛料がちょっと減ってきているわね。〈タウン?タヴァン〉の真南のういきょう小路にトルネドラ人の香辛料市場があるのよ。居酒屋《タヴァン》を見つけるのはお手のものでしょう」
「退屈な遠出になりそうだわい」老人は快活に言った。「それにさびしくもある。十リーグの長い道中、話し相手もいない」
「鳥を相手にしたらいいわ」ポルおばさんはそっけなかった。
「聞き手としては悪くないが、やつらのおしゃべりは同じことのくりかえしでたちまちつまらなくなっちまうのさ。その子を道連れにするのはどんなもんだろう?」
ガリオンは固唾をのんだ。
ポルおばさんは辛辣に言った。「この子はひとりでいても悪い癖を山ほど身につけているのよ。くろうとの教えをうけさせたくはないわ」
「マダム?ポル、そりゃ言いがかりだ」老人はほとんどうわの空で揚げ菓子をひとつくすねながら、反論した。「それにな、変化はいい影響を与えるぞ――視野を広げるともいえる」
「ガリオンの視野はじゅうぶん広いわよ、おあいにくさま」
ガリオンの心はしぼんだ。
「だけど」おばさんはつづけた。「かれが一緒に行けば、香辛料を買い忘れたり、あんたがビールで酔っぱらってコショウをクローヴやシナモンやナツメグと混同するのを防いだりする役には立ちそうね。いいでしょう、連れていきなさい。でも、いい、いかがわしい所へ連れこんだら承知しないからね」
「マダム?ポル!」老人はショックをそよおって言った。「そんな場所にわしが出入りしてるか?」
「あんたのことならよく知っているのよ、老いぼれ狼」彼女の口調はとりつくしまもなかった。「アヒルが池を好きなのと同じくらいあんたは自然と不道徳や堕落に魅せられるじゃないの。ガリオンをおかしなところへ連れこんだとわかったら、ただじゃすまないわよ」
「するとそういうことがあんたの耳にはいらんように気をつけなけりゃならんというわけだ」
ポルおばさんはかれをにらみつけた。「どの香辛料が必要か調べるわ」
「そしてわしはファルドーから馬一頭と馬車を借りてこよう」老人はそう言って、またひとつ揚げ菓子を盗んだ。
驚くほど短時間のうちに、ガリオンと老人は早足はねながら、アッパー?グラルトへの砂利道をたどっていた。晴れた夏の朝で、空にはタンポポの綿毛のような雲がうかび、灌木並木の下は深い青にかげっていた。しかし二、三時間もたつと太陽が暑く照りつけて、馬車にゆられているのが退屈になってきた。「もうすぐかな?」ガリオンがそう訊いたのは三度めだった。
「まだしばらくだ」老人は言った。「十リーグはかなりの距離だからな」
「あそこは前にいっぺん行ったことがあるんだ」ガリオンはなにげなく聞こえるように言った。「もちろんそのときはほんの子供だったからあまりおぼえていないけど、すごくいい所だったような気がするよ」
老人は肩をすくめた。「どこにでもあるような村さ」どことなくほかのことに気をとられているようだった。
ガリオンは長い道のりを忘れさせてくれる話をしてもらおうと、質問をはじめた。
「どうしておじいさんには名前がないの――こんなことを訊いて悪くなければ?」
「名前ならたくさんある」老人は白いあごひげをしごいた。「年の数に負けないぐらいな」
「ぼくはひとつだけだ」
「今までのところはな」
「え?」
Posted by childishgut at 12:34│Comments(0)